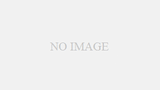「マルハラ」って言葉、最近よく耳にするけど、実際どうなの?って思っている人も多いはず。
マルハラはくだらなくて意味不明なのでしょうか?
また、いったいいつ生まれた言葉なのでしょうか?
何が話題なのか、なぜこんなに賛否両論なのか、解説していきます!
マルハラってどういうハラスメント?
「マルハラスメント」の略で、業務連絡の文末に「。」がつくだけで若者がビビる、っていう現象。
SNS全盛の今、コミュニケーションの取り方にも変化が出てきて、こんな新しい言葉が生まれたんですね。
文末の「。」、そんなに怖い?
昔ながらのメール文化と、SNSで育った世代とのギャップが生んだ、ちょっとした誤解かも?「。」がないとフレンドリー、あるとドキッとする…なんて、ちょっとおもしろいですよね。
文化の違いって、思わぬところで顔を出します。
LINEやメッセンジャーが普通になった今、新しいタイプのハラスメントが生まれたってわけ。時代の流れって面白いですよね。
マルハラを感じる?文章例を紹介!
- 業務連絡の場合
- 「プロジェクトの進捗報告を明日までにお願いします。」
- 「会議の資料、確認しました。修正点を直して再提出してください。」
- フィードバックの場合
- 「この案件、もう少し詳細な分析が必要です。」
- 「提出された報告書に不備があります。確認してください。」
- 指示の場合
- 「今週中にその件を解決しておいてください。」
- 「新しいガイドラインに従って、作業を進めてください。」
いつうまれた?
マルハラ、このちょっとクセのある言葉は、実はそんなに昔の話ではないんですよ。
2024年1月28日、AbemaTVのある番組で初めてこの話題が取り上げられたんです。
なんだか、昨日のことみたいに新しい感じがしますよね。
そして、Abemaがこの話題をニュースサイトに掲載したことで、一気に火がついたんです。
他のメディアも「マルハラって何?」と飛びつき、あっという間に話題の中心に。
つまり、このちょっとした現象が大きな波になったのは、ほんの数ヶ月前のことなんですよ。
時代の最先端をいく話題って感じで、わくわくしますよね!
マルハラはくだらなくて意味不明?反対派の意見を紹介
「マルハラって、ホントにそんなに大問題なの?ちょっとくだらないと思わない?」って感じの声が、反対派から聞こえてきますね。
この反対派、主に文末の「。」一つで大騒ぎすることに対して、眉をひそめてるわけです。
「まあまあ、そんなにカリカリしないでよ。文末にピリオドがあろうがなかろうが、大事なのは内容でしょ?」と、彼らは言いたいわけです。
結局のところ、業務連絡は業務連絡。文末に「。」があるからって、何が怖いの?っていうシンプルな疑問を投げかけています。
そして、「昔からメールだって、正式な文書だって、文末にはちゃんと句点を打つのが普通だったじゃない。
それが急にマルハラって、何の冗談さ?」というわけ。
つまり、彼らにとっては、古来からのコミュニケーションのルールが、いきなり問題視されること自体が意味不明なんですよね。
「ねえねえ、でもさ、絵文字やスタンプを業務メールで使い始めたら、それはそれで変じゃない?どうせ文句言うんでしょ?」って反論も。
この言葉からも分かる通り、どんなコミュニケーション方法をとっても完璧ってわけにはいかないし、結局は受け取る側の感じ方一つなのかもしれません。
要は、「人それぞれってことで、気楽にいこうよ。文末の「。」ぐらいでビビらないでさ。もっと大事なことがあるでしょ?」というのが、彼らの主張どこか懐かしい、昔ながらのコミュニケーションのスタイルを守りつつ、新しい時代の変化に少し困惑している感じです。
そう考えると、マルハラについても「くだらない」とか「意味不明」と切り捨てるのではなく、世代間での価値観の違いや、コミュニケーションスタイルの多様性を理解し合うことが大切なのかもしれませんね。
マルハラ賛成派の意見は存在する?
「え、マルハラ賛成派ってホントにいるの?」って思うかもしれないけど、実は「マルハラを理解しよう」という声もちらほら。
彼らは、マルハラを一種のコミュニケーションの改善と捉えているんですよ。
「さあ、ちょっと待ってよ。文末の『。』が苦手って声を無視するのは、もしかしたらコミュニケ
ーションのチャンスを逃してるかも?」というのが、彼らの考え方。
つまり、「マルハラっていうのは、私たちのコミュニケーション方法にもう少し柔軟性を持たせようよ」と提案しているわけです。
「ほら、みんなで気軽に話せる環境を作るって大事じゃない?『。』でビビっちゃう人がいるなら、それに対応するのもアリだと思うんだけどなあ」と、彼らは言います。
こうしてみると、賛成派の意見も一概に「マルハラを推進しよう」ってわけではなく、「若い世代の感覚を理解し、より良いコミュニケーションを目指そう」というポジティブな動機から来ているんですね。
「だってさ、LINEだってメールだって、結局は伝えたいことを相手に伝えるためのツールでしょ?だったら、相手がどんな形式であれ、快適に感じる方法でコミュニケーション取るのって、すごく大切だと思うんだけど」と、賛成派はさらに加えます。
この意見からは、時代に合わせてコミュニケーションスタイルをアップデートしていくことの重要性が伝わってきます。
結局、「マルハラ賛成派」っていうのは、マルハラを肯定しているわけではなく、「マルハラを通じて、もっと心地よいコミュニケーションを模索しよう」という意見を持つ人たちなんです。
「みんながストレスなく話せる世界っていいよね」というわけで、賛成派の意見にも、一考の価値があるかもしれませんよ。
マルハラはくだらなくて、意味不明?に関するまとめ
マルハラ問題は、文末の「。」を巡る世代間のコミュニケーションギャップを浮き彫りにしました。
賛否両論ありますが、根底にあるのは、変化する社会におけるコミュニケーション方法の多様性と柔軟性を受け入れ、理解し合うことの重要性です。